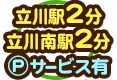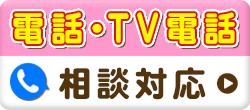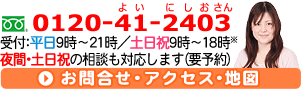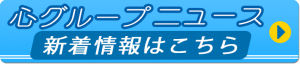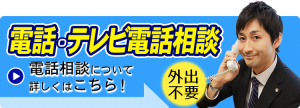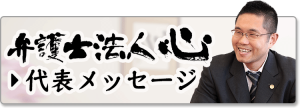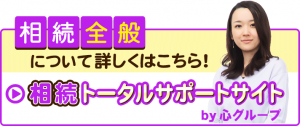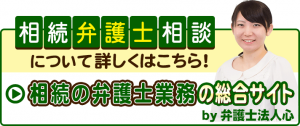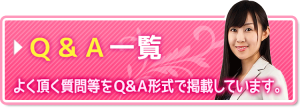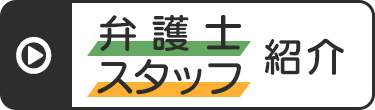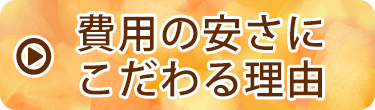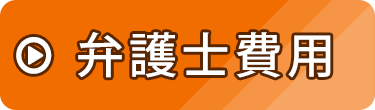被相続人が連帯保証人だった場合の相続放棄
1 被相続人が連帯保証人だった場合も相続放棄できる
被相続人自身が借金を抱えていた場合だけでなく、被相続人が誰かの連帯保証人になっていた場合も、相続放棄することで連帯保証人の地位を引き継ぐことはなくなります。
ですので、被相続人に特に財産がなく、生前から連帯保証人として支払いの請求を受けていたような場合は、相続放棄をするのが得策でしょう。
2 主債務者が返済を継続している場合
被相続人自身が借金をしている場合と比べて、被相続人が連帯保証人になっている事実は簡単にはわからないことがあります。
特に主債務者が返済を続けている場合は、返済されている以上連帯保証人に対して督促が来ることはないわけですから、郵便物などを確認しても連帯保証人になっていることは気づけないことが多いでしょう。
また、連帯保証人になっていることが判明した場合であっても、主債務者が問題なく返済していくことができそうなのであれば、必ずしも相続放棄しなくてもいいのでは、という考え方もあります。
経済的な損得だけで判断するのであれば、被相続人に財産がほとんどないのなら、現時点で連帯保証人として請求を受けていなくとも念のために相続放棄しておけば安全でしょう。
連帯保証人となっているかどうか不明という場合も同様で、相続するメリットがなく借金や連帯保証人となっている債務があるかもしれないというリスク(デメリット)だけがあるのであれば、相続放棄しておくと安全です。
3 被相続人の死亡後数か月以上経過してから連帯保証人となっていることが判明した場合
相続放棄は、相続人となっていることを知ってから3か月以内に行わないといけません。
しかし、被相続人に債務があることが当初わからず、相続人となっていることを知ってから3か月以上経過した後にそれを把握した場合には、例外的に3か月以上経過していても相続放棄できることがあります。
専門的かつ難しい問題になってきますので、被相続人が連帯保証人となっていたことで突如請求を受けることになってしまった、といった場合には速やかに弁護士へ相談して対応を考えた方が良いでしょう。