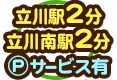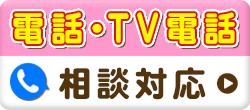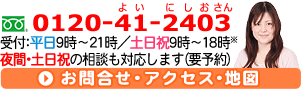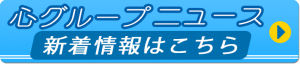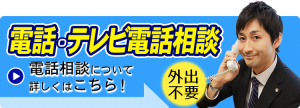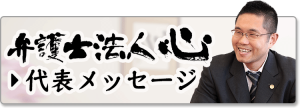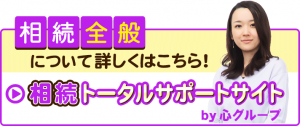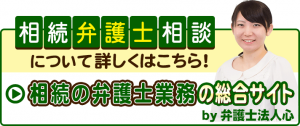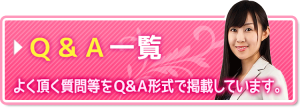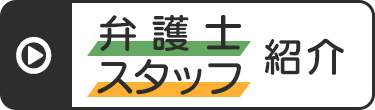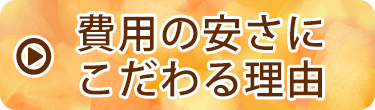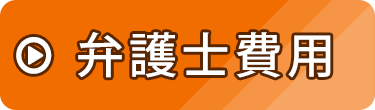相続放棄の回答書の書き方
1 回答書とは
相続放棄の申述を行うと、裁判所から回答書という書類が届くことがあります。
相続放棄は一切の資産・負債を承継しないという重大な意味をもつ手続きなので、裁判所の方から今一度意思確認を行うという意味合いがあります。
なお、裁判所によって意思確認の方法は異なり、電話で意思確認されることもあります。
また、弁護士に依頼して手続きしている場合は弁護士に対して確認がなされ、本人には特に連絡されないということもあります。
逆に言うと、弁護士に依頼している場合であっても、弁護士ではなく本人に対して裁判所から回答書が届くということもあります。
2 回答書の書き方
回答書は一般の方が記入することを想定しているものですので、決して難しい内容がかかれているわけではありません。
ですので、基本的には聞かれたことに素直に回答すれば問題ないです。
最初に裁判所に提出した書類の内容と矛盾が生じないよう、あらかじめ控えをとっておくとよいかもしれません。
3 特別な事情がある場合は注意
相続放棄は自身が相続人であることを知ってから3か月以内に行う必要があります。
そのため、被相続人が亡くなってから3か月以内であれば特に問題ないですが、これを過ぎている場合は“相続人であることを知ってから”3か月以内であることを示す必要があります。
相続人であることを知ってから3か月を経過している場合でも、事情によっては相続放棄できることがありますが、イレギュラーなケースですので回答書の作成は慎重に行うべきでしょう。
また、被相続人の財産を費消・処分してしまっている場合は相続放棄できませんので、そのような行為をしていないかの質問があります。
基本的に「費消・処分していない」と回答すれば問題ないですが、迷うような事情がある場合は慎重に記載した方が良いので弁護士等専門家へ相談された方がいいかもしれません。